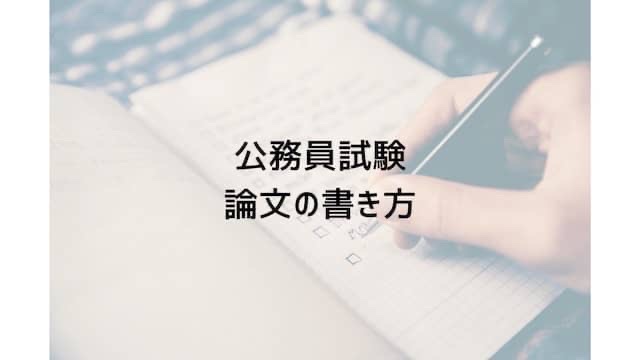
こんにちは、元公務員のヤット(@kantan-koumuin)です。
公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

こんな疑問を解決できる記事になっています。
本記事の内容
- 論文試験の6つの落とし穴
- 論文を書く際の注意点
- コツ
論文試験で最も大切なことは、不合格になるポイントを押さえることです。不合格になるポイントは決まっているので必ず避けなければなりません。
実際に、僕はポイントを押さえることによって政令指定都市(京都市、神戸市)等の難関試験を突破することができました。
本記事では、不合格になるポイントだけでなく、試験官に響く論文を書けるコツなども解説しています。
論文試験の全体像については、下記の記事でまとめています。書き方以外にも情報満載なので、併せて活用してください。
こちらもCHECK
-
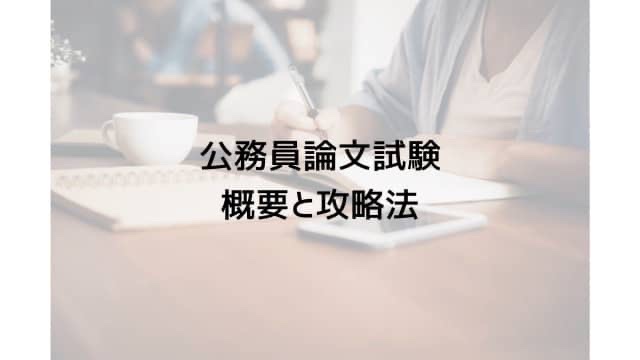
-
公務員論文試験のルールと不合格を防ぐ攻略法
続きを見る
もくじ
【前提】公務員試験論文の書き方の全体像

論文試験は、ほとんどの職種の公務員試験で採用されている試験になります。
そして、苦手としている受験生も多いのではないでしょうか。
まず、論文試験がうまく書けない受験生の特徴として、いきなり書き出してしまうということがありますね。
これは絶対NG。
イメージとしては、下記のとおり。

このようなイメージですね。
いきなり書き出すのではなく、上記のように必ず設計図を書き出してから、実際に書くようにしましょう。

設計図無しに家が建たないように、論文も設計図が無いと書けないのです。
【正解】公務員試験の論文は落とされない文章を書くこと

公務員試験の論文試験をうまく書こうとする受験生が多く居ますが、そんなことよりも大事なのが足切りで落とされない文章を書くことですね。
なぜなら、採点基準に最低限守っていなければならない事項があるから。
この事項を守れていなければ、せっかく書いた文章を全てチェックされることなく、途中で不合格の烙印を押されてしまいます。
①文字数が指定文字数の7割に満たない
例えば、指定字数が800文字の場合、最低でも560文字以上(800×0.7=560)は必要になりますね。
文字数が少ない=そこまで就職の意思がない
と判断されるので、6割以下はNG。
②字が汚すぎて試験官が読めない
字が汚いと、1文字も読まれることなく不合格になります。
字が美しい必要はありませんが、丁寧に書くことはできるはず。
字が汚いと認識している人は、丁寧に書く意識を持ちましょう。
③名前を書いてないため誰が書いたかわからない
「本当にこんな奴が居るのか?」と疑いたくなりますが、残念ながら毎年一定数居ますね。
そのため、答案用紙を受け取って試験がスタートしたら、真っ先に名前を書くようにしましょう。
緊張下では、信じられないようなミスが起こるもの。
④論点が課題と合っていない
例えば「あなたの考えを述べよ」と言われているのに、問題点を列挙するだけのような場合ですね。
その文章には問題点しか書かれていないので、論点が全く合っていません。
このような場合は「課題を理解していない」と判断されるので、不合格になります。
⑤文章の構成がめちゃくちゃで伝わらない
記事の冒頭でお伝えしていたように、しっかりと文章構成を練っていないため起こる現象。
文章の冒頭で、いきなり理由が書かれているような文章は非常に読みにくく、マイナス評価の対象です。
焦らず、自分が何を書くかハッキリさせてから書き始めましょう。
⑥最後まで書き上げられていない
このパターンも、最初に文章の設計図をしっかり練っていないため。
最初の段階で文章の設計図が出来上がっていれば、どれくらいの文字量と時間がかかるか大体把握できます。
この辺りを雑にしていると、そもそも最後まで書き上げられない。
どれだけ良い文章を書けていても、最後まで書けていなければ問答無用で不合格です。
まず、文章どうこうよりも上記の事項を最低守るようにしましょう。
最低限のラインを守れるようにならなければ、文章以前に不合格になってしまいます。
公務員試験の論文は「構成」が大切

構成とは、設計図で言うところの、
「必要事項を書き出す」
「結論を明確にする」
部分になりますね。
公務員試験には大きく、論文形式と小論文形式に分けられます。
上記の2つで解説していきます。
形式については、こちらの記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-

-
公務員教養試験の全体像と対策【具体的な勉強方法】
続きを見る
論文形式(上級・大卒)の書き方5ステップ
論文形式は、上級試験で頻出の形式となっています。
課題としては、ある問題について自分の意見を述べるといったもの。
ステップ①:課題を把握する(定義)
論文形式は、課題に対して
- どのような認識を持っているか
- どのように捉えているか
を最初に書き始めるのがベターですね。
例えば「高齢化とは〜」「温暖化とは〜」など、その課題が指す状況がどのようなものか、を客観的に分析して書くといった感じ。
主に、時事問題に関する知識や理解が必要なので、普段から新聞やニュースを聞いておかないと対応できませんね。
また、抽象的でなく自分の言葉でしっかりと意味を伝えられるようにしておかなければなりません。
ステップ②:なぜ、その問題が起こったのか捉える(背景)
問題が起きるのは必ず、原因があります。
なぜ、その問題が起きたのか分析して説明しましょう。
原因が分からなければ、解決に向けて具体的な行動を取れないため、原因追求は必要。
例えば、
「出生率の低下により、人口が減少し働き手が少なくなっている。減少に歯止めをかけるためには、出生率を上げるべきだ」
なんていう風に書けるわけですね。
ステップ③:今後起こり得る問題を予想する(問題提起)
このまま解決策まで行きたいところですが、少し我慢。
問題提起をすることによって、解決すべきことが見えてきますよね。
また「すでに問題になっているもの」も織り交ぜながら問題提起すると、より中身のある内容になります。
この時点で「定義」「背景」「問題提起」が終了。
この3つで序論になりますね。
理想的な文章量としては、論文全体の3割程度が良いでしょう。

ステップ④:問題の解決策を述べる(解決策)
論文の最も重要な部分と言っても過言ではないでしょう。
なぜなら、解決策こそ自分で提起した問題の答えに当たるから。
解決策を論じる前段階として、方向性や根拠を述べた後で、具体的な解決策を述べた方がより論理的で説得力のある文章になりますね。
文章量としては、論文全体の6割程度がベスト。
ステップ⑤:解決策と問題をまとめる(結論)
論文の最後には「まとめ」が必要というか、その方が綺麗な文章なんですよね。
注意したいのが、この部分までに相当の文章量になっているため、再度「問題+解決策」を詳しく書くのはNG。
例えば、
「少子化による問題は、今後悪化する可能性がある。少子化を防ぐためには、より一層の少子化対策の拡充が必要である」
のような感じですかね。
ちなみに、文章の締めは「今後〇〇職員として、社会に貢献していきたい」的な感じになるでしょう。

小論文形式(高卒・短大卒)の書き方4ステップ
小論文形式は、論文形式とは違い「自分の感じたこと」を述べることが多いです。
例えば、
- あなたがここ5年間で力を入れたこと
- あなたが思う理想の公務員像は
などが、小論文に当たりますね。
難易度は、論文形式に比べて低く比較的書きやすいと言われています。
しかし、文章構成が正しくないと論文同様に評価してもらえないので注意が必要。
ステップ①:自分の主張を述べる(結論)
論文形式とは打って変わって、結論から述べるべき。
なぜなら、試験官が最も聞きたいことは受験生の考えだから。
仮に「理想の公務員像を述べよ」という課題があったとしましょう。
例えば結論から述べると、
「私の理想の公務員像は国民の立場に立って行動できることです」
と、なるわけですね。
ステップ②:なぜ、そう思うのか述べる(理由)
その考えに至った理由があるはず。
例えば、
「国民の立場に立つことで、国民目線の行政が可能になるからです」
のような感じ。
理由が無いのに、自分の考えは主張できないので、理由はしっかりと説明できるようにしておきましょう。
ステップ④:具体的に説明する(根拠)
理由があったとしても、その理由が実際に効果があるのかどうか実証できませんよね。
具体性が無いと、小論文が全体的に抽象的になり、試験官の印象に残りにくくなってしまいます。
そこで、具体的な根拠を示すことによって、より筋の通った小論文に近づくことが可能。
例えば、経験や数値などは根拠になりやすいですよね。
ステップ④:再度、自分の主張を述べる(再結論)
文章の締めくくりは、小論文の冒頭に述べた結論を再度述べていきます。
理由や根拠を書いていくと、最終的に「あれ?結論ってなんだったけ?」となる危険性があります。。
そのため、試験官に自分の主張を印象付けるためにも、締めくくりで「だから私は〇〇だと思っています。」とするわけですね。
これは意外と効果的。

試験官は何百人の小論文をチェックするわけだから、少しでも文章の負担を減らしてあげたいところです。
再度結論を述べることよって、読みやすいから試験官の負担を減らすことができます。
公務員試験の論文を書くときの3つの注意点【公務員試験特有】

公務員試験に限らず、文章構成や誤字脱字などについて注意するのは当たり前。
しかし、それ以外にも注意するべき点があります。
公務員試験の論文は作文や大学のレポートと比べると、書き方が違うんですよね。
公務員試験ならではと言えるでしょう。
注意点①:公務員の立場になって書く
公務員試験の論文の多くは「〇〇としてどうするか」という課題が多い。
〇〇には、市役所職員や警察官が入る訳ですね。
要は「その立場に立って考えなさいよ」と言われているようなもの。
にも関わらず「国連と連携して〜」のような書き方をしてしまうと、現実的にはあり得ないのでマイナス評価になる可能性もありますね。
だからこそ、自分の志望先の取組みや関連する情報を把握しておく必要があります。
情報を少しでも知っていると、解決策が一気に書きやすくなりますよ。
注意点②:知識より自分の主張が大事
公務員試験の論文で、幾ら自分の知識を羅列したところで評価はしてもらえませんね。
なぜなら公務員試験の論文は、受験生の主張が最も採点ポイントになるため。
知識や教養は、主張を際立た出るための脇役に過ぎません。
自分の知識量よりも、何を考え、どうしたいのかを主張できるようにしましょう。

最低限は必要だけど、ほどほどで良いという感じです。
注意点③:一文を短く
書いている本人が気付きにくいのが一文の長さ。
一文を区切らず、一気に書いてしまう人が居ますが、読み手からすれば苦痛以外ありません。
例えば下記のような文章があったとしましょう。
読みにくい文章
今日は朝からスポーツジムに行って、筋力トレーニングをしたが、人が多くて思い通りのトレーニングができなかったけど、自分なりに工夫した結果、目標通りの体型と体重に近づいている気がする。
読みやすい文章
今日は朝からスポーツジムに行って、筋力トレーニングをした。人が多くて思い通りのトレーニングができなかったけど、自分なりに工夫した。その結果、目標通りの体型と体重に近づいている気がする。
いかがでしょうか。
読んでみると、わかると思いますが一文を区切るだけで全然違います。
少し意識するだけで、試験官の負担を減らすことに繋がるんですよね。
公務員試験の論文が全く書けない時のコツ

ここまで、公務員試験の論文の書き方の具体例を解説してきましたが、
「そもそも論文が書けない!」
「苦手だから、対策以前の問題なんだよ!」
こんな風に思っている、そこのあなた。気持ちは分かります。
かつての僕もそうだったから。
そこで、僕が実践して効果のあったコツをお伝えします。
上手な人の論文を読む・パクる
上手な公務員試験の論文は、合格するためのポイントをしっかりと押さえており、言わば模範解答ですね。
たしかに、記事の冒頭でお伝えしてきたようにな技術や知識を活かして、いきなり書いていくのはハードルが高い。
そこで、模範解答を読む、若しくはパクって書いて(写経)いきましょう。
それだけでも、テーマ毎の知識も身に付くし、文章の構成も理解できるようになるので一石二鳥です。

メモリーバブルを活用してみる
メモリーバブルと聞いて想像できる人は少ないでしょう。
言葉で説明するより、実際にメモリーバブルを見ていただきましょう。

こんな感じですね。
課題に対して、とにかく思い付いたことを書き出していきます。
雑に書くと把握しにくいので、丸で囲っておきます。
この丸が泡(バブル)のように見えることから、メモリーバブルと言っています。
課題を見て何も書けないという人は、下記の順番で実践してみてください。

慣れていないうちは、いきなり書いていくことは難しいです。
だからこそ、メモリーバブル等を活用して箇条書きで書き出していきましょう。
その文章の集合体が論文になります。
まとめ:コツをおさえよう!

公務員試験の論文は、ポイントを押さえていないと評価すらしてもらえないこともあります。
だからこそ、文章構成や注意点を理解していないと中々、論文のレベルを上げることができません。
この記事で解説した、書き方のステップを守りながら実際に書いてみてください。
まだまだ書くレベルに到達していない人は、メモリーバブル等を活用していきましょう。
まずは、書くことから全てが始まります。
論文試験のテーマを集めた記事を参考にしつつ、実際に書いていきましょう。