
こんにちは、元公務員ヤット(@kantan-koumuin)です。
公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

こんな疑問を解決できる記事になっています。
本記事の内容
- 解くコツ
- 解けない理由
- 勉強方法
資料解釈を苦手としている受験生は多いはず。なぜなら、いくら勉強しても全く得点が伸びないから。
実際のところ、資料解釈は数的推理と比べて高い計算能力が必要とされていません。
ちょっとしたコツさえ知っていれば、資料解釈は解けるようになります。
本記事を読んでいただければ、資料解釈が得点源になるはずです。
資料解釈は一般知能分野の中に含まれるため、他の科目も知っておいた方が効率的に対策することができます。
一般知能全体の情報を知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
>>【公務員試験】一般知能に地頭の良さは関係ない【数学0点の僕が解説します】
こちらもCHECK
-
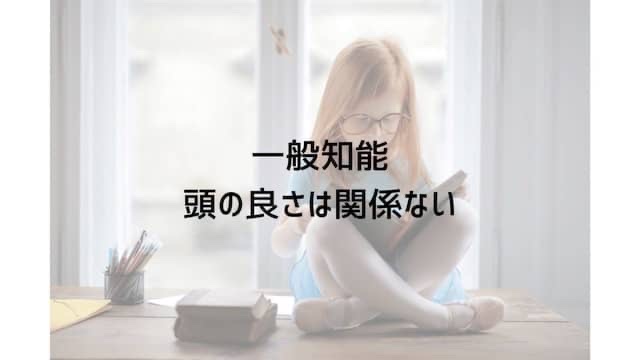
-
【公務員試験】一般知能に地頭の良さは関係ない【数学0点の僕が解説します】
続きを見る
もくじ
資料解釈ってどんな問題?【基礎知識を知っておこう】

資料解釈は、数的処理と呼ばれる分野の中に含まれる科目の1つになります。
数的処理には4つの科目があり、数的推理、判断推理、空間把握、そして資料解釈になりますね。

資料解釈の問題例
資料解釈の問題は膨大にありますが、今回は代表的な数表の問題を掲載しています。
ネット上で「資料解釈」と調べれば大量に問題例が出てくるので、すぐに見ることができますよ。

そしてある選択肢の中に下記のような選択肢があったとしましょう。
2005年のC工場の出荷額は、2000年のそれの3倍以上である
このような選択肢が5肢並んでいます。
資料解釈で求められる能力
資料解釈において、求められる能力は下記のとおり。
- グラフや表を読み取る能力
- 計算力
グラフや表を読み取る能力
資料解釈の問題は、とにかくグラフや表に書かれた大量の数字との戦いです。
問題を解いていくと感じるのですが、大量の数字から計算に必要な数字を見つけることが出来なければ、制限時間内に問題を解くことはできません。
計算力
計算に必要な数字を見つけることができれば、あとは計算するだけ。
しかし、適切な計算方法を知らないと一生かかっても問題を解くことはできません。
ここでの計算能力は単純な計算能力というより、単位を見て、適切な式で計算できるかどうかになります。
資料解釈の出題数
出題数は以下のとおり。
| 職種 | 問題数 |
| 国家一般職 | 3問 |
| 国家専門職 | 3問 |
| 東京都 | 4問 |
| 東京特別区 | 4問 |
| 裁判所事務官一般職 | 1問 |
| 地方上級 | 1〜2問 |
| 市役所 | 1問 |
多くて3問ですね。
どの試験でも資料解釈は1問以上出題されています。
ちなみに、職種によって出題されるパターンが決まっているようです。
そのため、自分が受験したい志望先の出題パターンは予め把握しておきましょう。

資料解釈を解くコツ

とりあえず「これさえ知っておけば解ける」というコツを解説していきます。
絶対にあり得ない選択肢を消去する
資料解釈の選択肢の特徴として、一般常識や社会情勢に言及したようなものがあります。
これ、一見すると正解のように見えますが、実は間違い。
間違い例
A工場の2011年の数値が落ち込んでいるのは、東日本大震災で被災し生産がストップしたからである。
このような文言は正解のように見えますが、そんなことは表やグラフから読み取ることはできません。
もし、このような選択肢があれば一瞬で消去しましょう。
選択肢を削っていくのは非常に大切で、考えるまでもなく選択肢を消去できるのは資料解釈くらいなものです。
雑に計算しよう
「雑」という言葉に違和感を覚えるかもしれませんが、実際のところ雑に計算しないと3分台で問題を解くことはできません。
例えば下記のような問題があったとしましょう。
19,800×5
資料解釈に慣れていない受験生はバカ正直に、このまま計算してしまいます。
こういった計算はとにかく、もっと雑に計算しましょう。
僕なら下記のように考えます。

計算を省略している部分もありますが、上記では小数点を無くしてから計算しています。
この方法だと計算はほとんど使っていません。これが資料解釈で使う「雑さ」になります。
資料解釈が全く解けない2つの理由

資料解釈がいつまで経っても解けない、安定して得点できない人は以下に該当している可能性が高い。
理由①:解法パターンを理解していない
数的処理の問題には全て解法パターンが存在しています。
これは資料解釈も同じ。
Yahoo!知恵袋を見ていると同じような質問が並んでいます。

このように個別の質問ばかりが目立ちますよね。
ここで質問している人たちは、個々の問題を理解していないのではなく、そもそも解法パターンを理解していない可能性が高い。
そのため、このように問題ごとに分からない部分が出てくるのです。
解法パターンをしっかりと学習していれば、このような質問をする必要は無くなります。
資料解釈には代表的な問題があります。
例えば「増加率・減少率」「指数」「実数」「構成比」等があります。
これらの問題名を知らないということは、解法パターンを知らないのと一緒です。
理由②:バカ正直に計算している
資料解釈は、とにかく雑に、そして楽に計算するように心がけましょう。
正攻法で計算してしまうと恐ろしほど時間がかかってしまいます。
問題を繰り返し解いて、どのような計算で雑さを出せるか把握しておく必要があります。
資料解釈の得点を伸ばす5つの勉強方法

資料解釈を勉強する上で、意識してほしいポイントがあります。
- 解法パターンを理解する
- 罠を見抜けるようにしておく
- 雑な計算を身に付ける
- 過去問を解きまくる
- 1問解くのにかかる時間を測っておく
順番に解説していきますね。
①解法パターンを理解する
まずは、解法パターンを徹底的に頭に叩き込みましょう。
資料解釈は、数的推理ほど数学的な知識は要りません。
頻出の「増加率」や「指数」等の解法パターンを知っているだけで、驚くほど得点できるようになります。
②罠を見抜けるようにしておく
資料解釈はとにかく罠が多い。
前項で解説したような「社会情勢や一般常識」もその1つ。
それ以外にも数多くの罠が隠されているので、1つでも多くの罠を知っておきましょう。
③雑な計算を身に付ける
3分台で解くためには、雑な計算をできるようにしましょう。
小数点を無くして計算したりと、その方法は人それぞれ。
自分流の雑計算を持っていると得点できる可能性は高くなりますよ。
④過去問を解きまくる
②と③に関しては、過去問を解かない限り絶対に身に付きません。
とにかく過去問を解いて解いて、解きまくる。
泥臭く問題を解いていくことが、得点に結びついていきます。
⑤1問解くのにかかる時間を測っておく
過去問を解いて、慣れてくれば必ず問題を解く時間を測っておきましょう。
試験本番では、いちいち時間を気にしてもいられません。
そのため、練習で時間を肌感覚で分かるようにしておくと良いでしょう。
まとめ:資料解釈は費用対効果が高い科目!

資料解釈を苦手としている受験生は多いですが、しっかりと理解し勉強方法さえ間違えなければ得点することが可能です。
資料解釈は問題数が少ないため、あまり重要視されていませんが、実は解法パターンの個数も少ないため一度理解してしまえば高確率で問題を解くことが可能。
つまり、非常に費用対効果が高い問題なのです。多くの受験生はここに気付いていない。
この記事を読んでいただけた、あなたは間違いなく一歩リードしているでしょう。