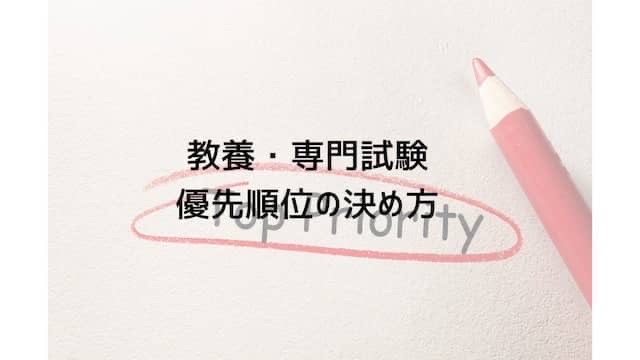
こんにちは、元公務員のヤット(@kantan-koumuin)です。
公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

こんな疑問を解決できる記事になっています。
本記事の内容
- 出題科目一覧表
- 優先順位の決め方
- 教養・専門試験の総合的な優先順位
公務員試験には筆記試験があり出題範囲は多岐に及びます。
これから公務員試験対策を始める人にとっては、対策すべきことが多すぎて混乱してしまいますよね。
そこで、本記事では対策を進める上で重要な「勉強の優先順位」について、コツや優先順位の決め方を解説しています。
優先順位を決めるポイントは以下の2つ。
- 得意不得意で優先順位を決めない
- 出題数が多い科目に注目
以上の2つを基準に対策を進めると、最も効率的に勉強できるようになります。
これから公務員試験に挑む人は、ぜひ参考にしてみてください。
公務員試験の全体の内容については、下記の記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-

-
公務員試験の内容と合格するための5つのポイントを解説
続きを見る
もくじ
公務員試験における出題科目

公務員試験は、とにかく科目数が多いのが特徴です。
公務員試験には教養試験と専門試験の2つがあり、その出題数は相当なもの。
この2つを合わせると30科目近くになります。そのため出題範囲も広範囲に及び全てを勉強しようとすると、時間が幾らあっても足りません。
まずは、自分が受験しようとしている試験にどのような科目があるかしっかりと把握しましょう。
教養科目
公務員試験における教養科目は、職種に関わらず多くの試験で採用されている科目になります。
消防官、警察官、市役所職員を始め皇宮護衛官などの試験において、専門科目がなく教養科目のみの試験もあります。
つまり、教養科目ほぼ必須と言っても過言ではありません。

ここからは教養科目の詳細に迫っていきましょう。
教養科目は大きく分けて以下の2つに分けられます。
教養科目
- 一般知能分野
- 一般知識分野
一般知能分野は主に数的推理や文章理解といった科目があり、一般知能分野は社会科学や人文科学といった科目が出題されます。
- 一般知能=計算系
- 一般知識=暗記系
と思っていただいて良いかなと。合格ラインは6割の得点を目指しましょう。
近年では一般知識を廃止しているしている自治体もあるので、受験先の出題範囲は確認しておいた方がベターです。
専門科目
公務員試験の専門科目は、大卒程度の国家公務員試験や政令指定都市の公務員試験で採用されています。
専門科目は、教養試験とは異なりどの区分を受験するかによって出題科目が変わるのも特徴ですね。
合格ラインは7割の得点と言われています
専門科目は大きく3つに分類されます。
専門科目
- 行政
- 法律
- 経済
この3つですね。専門科目は基本的に暗記系の科目になります。
試験科目については、こちらの記事で詳しく解説しています
>>【地方公務員】地方上級の試験科目を型ごとにまとめて図解で解説
こちらもCHECK
-

-
【公務員試験】地方上級試験科目の対策法と型ごとの解説
続きを見る
【公務員試験】出題科目の一覧表(出題数)

本章では、出題科目を一覧表にしています。
公務員試験で代表的な「国家一般職」「地方上級」「市役所」を例にして作りました。
上記3つはある程度、試験に共通している部分が多いので参考にしてみてください。
教養試験
| 教養科目 | 科目一覧 | 国家一般職 | 地方上級(全国版) | 市役所(A日程) |
| 文章理解 | 現代文 | 6 | 3 | 3 |
| 英文 | 5 | 5 | 3 | |
| 古文 | 0 | 1 | 1 | |
| 数的処理 | 判断推理 | 8 | 9 | 7 |
| 数的処理 | 5 | 6 | 5 | |
| 資料解釈 | 3 | 1 | 1 | |
| 社会科学 | 政治 | 1 | 1 | 0 |
| 経済 | 1 | 3 | 1 | |
| 法律 | 1 | 3 | 2 | |
| 時事 | 3 | 4 | 4 | |
| 自然科学 | 数学 | 0 | 1 | 1 |
| 物理 | 1 | 1 | 1 | |
| 化学 | 1 | 2 | 1 | |
| 生物 | 1 | 2 | 1 | |
| 地学 | 0 | 1 | 2 | |
| 人文科学 | 日本史 | 1 | 2 | 2 |
| 世界史 | 1 | 2 | 2 | |
| 地理 | 1 | 2 | 2 | |
| 文学・芸術 | 0 | 1 | 1 | |
| 思想 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 40 | 50 | 40 | |
専門試験
| 教養科目 | 科目一覧 | 国家一般職 | 地方上級(全国版) | 市役所(A日程) |
| 行政 | 行政 | 5 | 2 | 2 |
| 政治学 | 5 | 2 | 2 | |
| 社会政策 | 0 | 3 | 3 | |
| 国際関係 | 5 | 2 | 2 | |
| 法律 | 憲法 | 5 | 4 | 4 |
| 行政法 | 5 | 5 | 5 | |
| 民法 | 5+5 | 4 | 4 | |
| 労働法 | 2 | 2 | 2 | |
| 刑法 | 0 | 2 | 2 | |
| 経済 | ミクロ経済学 | 5 | 9 | 11 |
| マクロ経済学 | 5 | 9 | 11 | |
| 財政学 | 5 | 3 | 3 |
※社会科学、経済学など表に記載されていない科目あり。
※選択制を採用している試験あり。
上記の一覧表は、あくまで代表的な試験の出題数を記載しています。
必ず自分で志望先の出題科目と出題数を確認しましょう。
教養・専門科目で勉強の優先順位を決める理由

公務員試験において、勉強の優先順位を決めることは大切です。
何故なら、公務員試験は出題範囲と出題数が膨大なため全てを勉強することはできないから。
上記でも解説しましたが、教養・専門試験を含めると約30科目あります。
この全てを半年や1年で勉強できるでしょうか?
答えはNOのはず。
公務員試験に合格している数多くの受験生は必ず、勉強の優先順位を決めています。
もちろん僕も優先順位を決めて勉強するようにしていました。
これから勉強を始めようとする人は必ず科目に優先順位を決めて、勉強していきましょう。
優先順位を決める際の3つルール

優先順位を決めると言っても「何となく」順位を決める訳ではありません。
そこには明確なルールが存在しています。1つずつ確認していきます。
①自分の受験する試験を調査する
まずは志望先の試験の出題科目を調べましょう。
基本的には志望先名称をインターネットで調べれば、必ず試験情報が記載されています。
出題数の詳細は記載されていないことが多いですが、ある程度予想できるので問題ありません。
調査することから全ては始まります。
②得意不得意で優先順位を決めない
不得意だからと言って、勉強を後回しにすると場合によっては取り返しのつかないことになります。
どのような人にも、科目によっては得意不得意があると思います。
- 昔から数学が苦手だったから、数的は後回しで良いや。
- 暗記が苦手だから法律系はやらない。
このようになってはいませんか?
ちなみに上記で挙げた数的や法律系は、出題数が多く合否に関わってくる重要科目になります。
もし、仮に不得意だからという理由で勉強を後回しにしていると、間違いなく他の受験生に引き離されます。
逆も然りです。
自分が得意か不得意かで、勉強の優先順位は決められないので注意しましょう。
③出題数で優先順位を決める
勉強の優先順位の決め方の基本は出題数です。これ以外にありません。
例えば、地方上級の試験を受験するとしましょう。
数的処理の出題数は大体、
- 判断推理8〜9問
- 数的推理5〜6問
- 資料解釈1〜2問
と予想されます。
出題数から勉強の優先順位を決めるので、間違いなく判断推理と数的推理の科目から勉強していきますね。
具体的に勉強時間でイメージすると下記のとおり。
3科目を1時間勉強するなら、
- 判断推理30分
- 数的推理20分
- 資料解釈10分
みたいな感じです。
極端な話、資料解釈は1つの試験で2問弱しか出題されないのにも関わらず、資料解釈を1日中勉強していると効率の良い勉強とは言えませんよね。
出題科目と出題数から考えて、勉強の優先順位を決めていきましょう。

数的推理については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>数的推理が難しく感じる2つの理由と数的推理の対策法【初心者向け】
こちらもCHECK
-

-
数的推理が難しく感じる2つの理由と数的推理の対策方法
続きを見る
教養科目の勉強優先順位【科目ごと】を解説

教養科目の優先順位は以下のとおりです。

このようなイメージですね。
分かりやすくするため、教養科目は「数的推理・判断推理」「文章理解・資料解釈」「その他」に分けて解説していきます。
数的処理(優先度:高い)
数的処理を最優先する理由は、出題数が多く配点で言えば3分の1を占めるため。
この数的処理で確実に得点できるようになっておくことで、合格への可能性がグッと近づきます。
可能な限り毎日問題を解き必ず、解法パターンを頭に叩き込むようにしておきましょう。
文章理解、資料解釈(優先度:普通)
文章理解には英文と現代文があり、問題数を合わせると10問を超える試験もあります。
問題形式は長文が多く、英単語さえ暗記しておけば解けるような問題もありますね。
文章理解も解法パターンが存在し、理解さえすれば安定的に得点することが可能です。
③その他(優先度:低い)
最後は知識系になります。
知識系はピンポイントに暗記しておかなければ得点することができません。そのため、運の要素が強い問題と言えます。
そのような問題が合否に大きく関わることは少ないため優先度を低く設定しています。
また、知識系は基本的に暗記のため最初の方に勉強してしまうと、必ず忘れてしまうため直前期に勉強するのも作戦としては良いと言えます。
図解には、社会や政治等を「優先度:普通」の場所に持ってきています。これは出題数が多いためです。
しかし、上記で解説している通り基本的に暗記科目なので、1日に勉強するウェイトは低くても構いません。
そんなことよりも数的処理の解法パターンを1つでも多く理解するようにしましょう。
専門科目の勉強優先順位【科目ごと】を解説

専門科目は「法律系」「経済系」「行政系」の3つの分類に分けて解説していきます。

法律系

法律系科目は、憲法から勉強していきましょう。
何故なら、行政法や行政学、政治学の分野は憲法の知識が備わっていないと理解しにくいためです。
また判例問題が多く、具体例とセットで暗記すれば効率よく勉強することが可能。
民法は私たちの生活に密接な関係にある問題だけに事例問題も多く、十分な理解が必要な科目と言えます。
憲法の基礎知識を基に地道に解いていきましょう。
経済系

ミクロ→マクロ→財政学の順番がおすすめです。
何故なら、抽象度の高いマクロ経済学は、経済の基礎的な考え方が備わっていない段階では理解しにくいため。
- ミクロ経済学=経済の基礎的な知識(個人や企業)
- マクロ経済学=国全体といった抽象的な分析
なので、ミクロの知識があることが効率の良い学習のポイント。
財政学は、経済学で学ぶ論点をさらに深く掘り下げる分野があるため。
先に経済学を学んでおくことによって、財政学の学習をスムーズに学ぶことができます。
行政系

政治学の理解があることで、教養科目の社会科学や時事等の理解にも繋がります。
また、政治学は行政学や社会学と重複する分野もあり効率的に学習することができますよ。
行政学は、政治学と関係が深い科目と言えますね。
社会政策と国際関係は、出題数が少ないため後回しにしても問題はなし。
しかし、教養科目や時事にも関連があるため軽視はできません。
教養・専門科目の全体の優先順位

公務員試験の種類によっては、教養・専門試験両方出題されるものもあります。
科目全体の「憲法・行政法・民法」〜「ミクロ・マクロ」を「数的処理」と並行しながら学習するのが良いでしょう。
並行しての学習は、一体自分が何処まで学習したか分かりにくく混乱し易いので注意が必要です。
不合格になってしまうパターンは、一度に多くの科目に手を出してしまうことです。
優先順位を意識しつつ、基礎を先に固めて勉強するようにしましょう。
捨てる科目も決めていく

教養科目と専門科目を両方の科目を全て勉強することは不可能です。
そのため「捨てる科目」を作っておきましょう。
捨てるかどうかの判断基準は優先順位を決めた際のルールと同じく出題数です。
また、時代によって出題されない問題もあるため注意しておきましょう。
例えば教養であれば、
- 文章理解(古文)
- 判断推理(家系図)
- 物理
- 数学etc
このような感じになります。
古文は1問しか出題されない上に出題すらされない試験もあります。
また判断推理の家系図の問題も時代に合っていないため、出題される機会が減ってるんですよね。
このような問題は積極的に捨てていきましょう。
出題されたとしても他の受験生も得点出来ないので差が広がる心配はありません。
捨てる科目は受験生によっても異なるので、本当に勉強すべき科目や問題なのかは、勉強を持続させながら決めていきましょう。
まとめ:優先順位に注意しよう!

公務員試験の勉強を初めてする人にとって、勉強の優先順位を決めるのはハードルが高いと言えます。
この記事を見ていただいて、少しは参考になるでしょう。
記事の要約
- 勉強の優先順位は、出題数で判断する
- 得意不得意で優先順位を決めない
- 専門科目は勉強の順番に注意する
これから勉強を始めていく人は、必ず優先順位を決めてから始るようにしましょう。
優先順位を決めることによって効率の良い勉強が可能となり、30科目にも及ぶ公務員試験を突破することに繋がります。