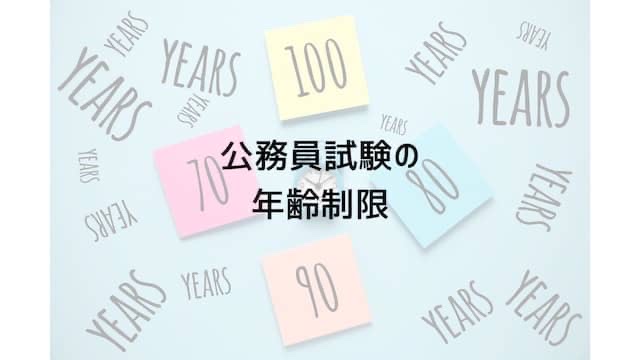
こんにちは、元公務員のヤットです。
公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。
私は30歳を超えているのですが、受験できるでしょうか?

こんな疑問を解決できる記事になっています。
本記事の内容
- 年齢制限がある理由
- 注意点
- 上限年齢一覧表
公務員試験には年齢制限(上限)があります。
概ねですが、国家公務員は30歳前後、地方公務員は40歳前後となっています。
既卒や社会人の受験生の方は、年齢が気になったり納得できないこともありますよね。
本記事では、年齢制限がある理由や上限年齢が一目でわかる一覧表を作成しました。
特に社会人の受験生の方は、本記事を読んでいただければ年齢を気にすることなく勉強できるようになります。
※一覧表では官公庁の公式サイトのリンクを貼っているので、気になる方はリンクをクリックしてください。
もくじ
公務員の年齢制限一覧表

本章では、国家公務員と地方公務員に分類して上限年齢を一覧表にまとめています。
受験の可否を確認する際に活用してください。
国家公務員
国家公務員は、行政府・司法府・立法府に分類されます。
行政府(人事院)
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 国家総合職 (院卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 国家総合職 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 国家一般職 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 国家一般職 (社会人経験) | 40歳 | 採用ページ |
| 国税専門官 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 財務専門官 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 法務省専門職員 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 皇宮護衛官 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 航空管制官 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 海上保安官 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
司法府(裁判所)
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 裁判所総合職【裁判所事務官】 (院卒者) | 30歳 | 採用ページ |
| 裁判所総合職【家裁調査官補】 (院卒者) | 30歳 | 採用ページ |
| 裁判所総合職【裁判所事務官】 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 裁判所総合職【家裁調査官補】 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
| 裁判所一般職【裁判所事務官】 (大卒程度) | 30歳 | 採用ページ |
立法府(衆議院・参議院)
地方公務員
北海道・東北エリア
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 北海道 (一般行政A) | 30歳 | 採用ページ |
| 青森県 (行政) | 32歳 | 採用ページ |
| 岩手県 (一般行政A) | 35歳 | 採用ページ |
| 宮城県 (行政) | 35歳 | 採用ページ |
| 秋田県 (行政AB) | 34歳 | 採用ページ |
| 山形県 (行政) | 39歳 | 採用ページ |
| 福島県 (行政事務) | 35歳 | 採用ページ |
関東・甲信越エリア
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 茨城県 (事務) | 29歳 | 採用ページ |
| 栃木県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 群馬県 (行政事務) | 29歳 | 採用ページ |
| 埼玉県 (一般行政) | 30歳 | 採用ページ |
| 東京都 (I類A) | 31歳 | 採用ページ |
| 千葉県 (一般行政A) | 30歳 | 採用ページ |
| 神奈川県 (行政) | 30歳 | 採用ページ |
| 山梨県 (行政I・II) | 35歳 | 採用ページ |
| 長野県 (行政A) | 35歳 | 採用ページ |
| 新潟県 (一般行政A・B) | 30歳 | 採用ページ |
中部・北陸エリア
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 富山県(総合行政) 35歳 | 35歳 | 採用ページ |
| 石川県(行政) 29歳 | 29歳 | 採用ページ |
| 福井県(行政) 34歳 | 34歳 | 採用ページ |
| 岐阜県(行政I) 29歳 | 29歳 | 採用ページ |
| 静岡県(行政I・Ⅲ) 28歳 | 28歳 | 採用ページ |
| 愛知県(行政I・Ⅲ) 29歳 | 29歳 | 採用ページ |
| 三重県(行政Ⅱ) 29歳 | 29歳 | 採用ページ |
近畿エリア
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 滋賀県 (行政A) | 35歳 | 採用ページ |
| 京都府 (行政IA) | 35歳 | 採用ページ |
| 大阪府 (行政) | 34歳 | 採用ページ |
| 兵庫県 (行政A) | 27歳 | 採用ページ |
| 奈良県 (行政A・B) | 29歳 | 採用ページ |
| 和歌山県 (一般行政職) | 35歳 | 採用ページ |
中国・四国エリア
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 鳥取県 (事務) | 35歳 | 採用ページ |
| 島根県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 岡山県 (行政) | 30歳 | 採用ページ |
| 広島県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 山口県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 徳島県 (一般事務) | 36歳 | 採用ページ |
| 香川県 (一般行政事務) | 29歳 | 採用ページ |
| 愛媛県 (行政事務A) | 34歳 | 採用ページ |
| 高知県 (行政) | 34歳 | 採用ページ |
九州・沖縄エリア
| 職種 | 上限年齢 | 公式サイト |
| 福岡県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 佐賀県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 長崎県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 熊本県 (行政) | 35歳 | 採用ページ |
| 大分県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 宮崎県 (一般行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 鹿児島県 (行政) | 29歳 | 採用ページ |
| 沖縄県 (行政I) | 35歳 | 採用ページ |
公務員試験の年齢制限

公務員試験には年齢制限があり、制限に泣かされている受験生は多くいます。
実は年齢制限がある理由が明確にあり、受験生は受け入れるしかありません。
本章では、年齢制限について法律などを噛み砕いて簡単に解説しています。
制限がある理由
公務員とは異なり、民間企業では雇用対策法10条により年齢制限を設けることは原則禁止されています。
しかし、公務員は別で雇用対策法38条2項により雇用対策法10条は適用されません。
つまり、公務員試験においては年齢制限を設けてOKということです。
その背景には以下の3つの理由があります。
- 教育に長期間要する
- 均一性を確保する
- 体力的
教育に長期間要する
公務員は、様々な法律・専門知識を深く広く身に付ける必要があります。そのため、一人前の公務員と認めてもらうためには長期間の時間を要します。
例えば、家庭裁判所調査官は2年にも及ぶ研修期間があり、採用されてもすぐに現場で働くことはできません。
均一性を確保する
例えば、高卒試験に大卒資格のある23歳以上の受験生が殺到すれば、高校生は太刀打ちできません。
一般的に大学を卒業していれば学力はもちろんですが、一般教養も身に付けており高校生とは歴然の差があります。
仮に年齢制限を設けていなければ、上記のような事態は頻発するでしょう。
そのため、年齢制限を設け高卒試験では18歳〜22歳、大卒試験は22歳以上という制限などが設けられています。
体力面
特に公安職と呼ばれる公務員は、年齢制限が厳しく設定されています。
消防士であれば過酷な現場から人命を救助しなければなりません。
高年齢になればなるほど体力は衰えていくので、行政系に比べて制限が厳しいのです。
近年では公安職の年齢制限は引き上げられる傾向にあります。
社会人の受験生はチャンスといえるでしょう。

注意点
年齢制限は、試験合格後に採用される時の年齢が原則です。
受験時に年齢制限をクリアしていても、採用時に年齢制限が超えている場合は受験できません。
各公務員試験の受験案内には、必ず年齢が記載されているので注意して確認しましょう。
神戸市の採用ページには、下記のように記載されています。

神戸市公式サイトより
基本的に採用時の年齢が記載されているので、自分の誕生日と比較してください。
年齢制限については、社会情勢などを考慮して引き上げや引き下げが実施されます。
不定期で実施されるので、注意してください。
各公務員の特徴

本章では、国家公務員や地方公務員など、各公務員の特徴について解説していきます。
国家公務員
国家公務員の上限は30歳前後となっています。
2023年度試験では平成5年生まれ、かつ大卒であれば受験できるようになっています。
また、国立国会図書館職員については34歳まで受験可能となっています。
国家公務員は地方公務員と異なり、新卒採用の傾向が強いため上限は30歳前後です。
地方公務員
地方公務員は国家公務員と比べ、上限年齢が高い傾向にあります。
地方公務員は以下の種類に分類されます。
- 都道府県
- 政令指定都市
- 東京特別区
- 政令市以外の市町村
特に政令指定都市以外の市町村の上限年齢は高くなっています。
理由としては、人口減少による過疎化が進み自治体での人材が不足していることが考えられます。
職種や場所にこだわりがなく「とにかく公務員になりたい!」という人は、政令市以外の市町村は狙い目です。
公安職
公安職は事務系に比べて体力を使うため、年齢制限も低めに設定されていました。
しかし、近年大幅に年齢制限が引上げられています。
特に警察官は多くの都道府県で35歳まで受験できるため、社会人からでも公安職に就くことが可能です。
消防官でも、東京消防庁の採用試験では35歳までの年齢引上げが発表されました。

東京消防庁の年齢制限に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
>>東京消防庁の年齢制限が大幅に緩和!35歳で消防官になる方法を解説
準公務員
準公務員は、民間企業でありつつ公共性や公益性の高い仕事です。
例えば、国立大学法人や文部科学省関連の職員などが該当します。
上限年齢は概ね29歳までとなっています。
一部の試験では39歳以下でも受験可能となっています。(例:日本学生支援機構・総合職)
独立行政法人では筆記試験で公務員試験と同様の試験が課されるため、難易度は高めです。
まとめ:最短で公務員合格を目指そう

年齢制限が引き上げられ、社会人・既卒者への期待はますます高まっている傾向です。
しかし、最短で合格を目指さないとライバルが増えていき、難易度が上がってしまいます。
前章で解説したように、公務員予備校などを積極的に活用しましょう。
年齢について考えすぎず、まずは目の前の試験対策に集中してください。
戦い方を間違えなければ、十分に合格の可能性はあります。
具体的な勉強時間などを知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。