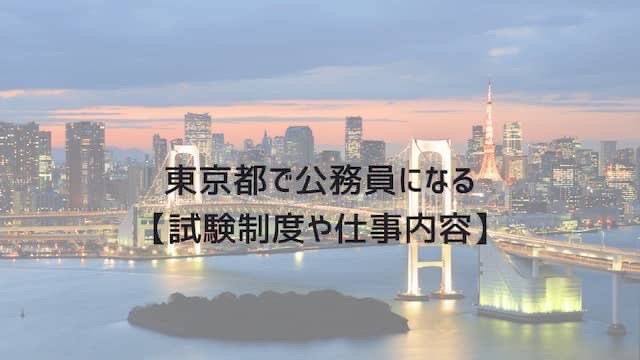
こんにちは、元公務員のヤット(@kantan-koumuin)です。
公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

本記事の内容
- 都庁と特別区のちがい
- 仕事内容
- 試験制度
東京都で公務員になるためには、いくつもの試験を突破していく必要があります。
最も有名な職種は、都庁職員ですよね。しかし、その他にも特別区職員などもあり他都市と比べ若干複雑です。
「東京都で公務員になりたい!」という人は、本記事を参考に試験対策を進めていきましょう。
本記事では、東京都庁職員にスポットを当てて解説しています。
目次
東京都・公務員の種類

東京都で公務員として働く場合、多くの職種があり複雑です。
例えば、以下のような職種があります。
- 都庁職員
- 特別区職員
- 公安系(東京消防庁職員など)
本章では、混同しがちな都庁と特別区のちがいについても解説しています。
東京都の公務員の職種については、下記の記事をご覧ください。
>>東京都の公務員って何種類ある?【職種ごとに解説してみた】
都庁職員
都庁職員は地方公務員ですが、仕事の中で都民と関わることはほとんどありません。
なぜなら、仕事のスケールが大きいため仕事の相手は国や民間企業などになります。
主な仕事
- 市区町村を越えたインフラ整備
- 都市計画
- 教育
- 治安維持
- 危機管理
- 国や企業との調整事務
上記のようにスケールの大きさが特徴です。
特別区職員
東京には特別区と呼ばれる、特別な行政区が設けられています。
例えば、渋谷区や板橋区、港区など。政令市でも行政区が存在しますが、特別区は別物。
東京の場合は、特別区1つ1つが政令市のような業務を担当しているイメージ。
主な仕事
- 生活保護
- 児童福祉
- 保育園の整備
- 証明書の発行
- ごみ処理やリサイクル関連業務
仕事の内容としては、一般的な市役所と同様で区民の生活に直結する業務を担当しています。
市役所の仕事については、市役所の仕事内容と1日の流れ【市役所の仕事は本当につまらないの?】で詳しく解説しています。
公安系(東京消防庁職員)
本来であれば、都の職員ですが公安系は異なります。
代表的なものが東京消防庁。首都東京を守る消防官たちです。
東京都内で発生するあらゆる災害に対応し、東京都のみならず日本全国で活動しています。
東京消防庁は都庁には属さず、独立して消防業務を担っています。
東京消防庁に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
>>東京消防庁の総合情報【仕事内容・採用試験・年収】全て解説します
東京都職員の年収

東京都の平均年収は、約750万円。
年収は大手企業と同程度か、少し劣るくらいです。しかし福利厚生などを考えれば圧倒的に安定していますよね。
下記の表をご覧ください。
| 区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 一般行政職 | 316,417円 | 453,549円 | 約7,483,558円 | 42.3歳 |
| 警察職 | 323,408円 | 514,842円 | 約8,494,893円 | 39.6歳 |
| 小中学校教育職 | 337,226円 | 434,470円 | 約7,168,755円 | 40.1歳 |
| 高等学校教育職 | 353,903円 | 454,477円 | 約7,498,870円 | 44.1歳 |
| 技能労務職 | 288,149円 | 388,154円 | 約6,404,541円 | 50.4歳 |
職種ごとの大まかな年収に関係する数値になります。
年収については、個人の属性により大きく異なるため参考程度にとどめてください。
都庁職員の年収については、東京都職員の年収まとめ【東京で生活できるか検証してみた】をご覧ください。
採用試験の中身

東京都職員になるためには、必ず公務員試験を受験しなければなりません。
本章では、採用試験の内容を解説していきます。
採用試験は区分ごとに実施され、下記のような職種があります。
採用試験の区分
- Ⅰ類A採用試験
- Ⅰ類B採用試験(一般方式)
- Ⅰ類B採用試験(新方式)
- 2類採用試験
- 3類採用試験
- 障がい者採用選考
- キャリア活用採用選考
- 就職氷河期世代採用試験(Ⅰ類B・3類)
- 任期付職員採用試験
例えば、大卒者が対象の1類A採用試験では、1次試験と2次試験が実施されます。
1次試験
- 教養試験
- 専門試験
- 論文
2次試験
- 口述試験
職種ごとに試験が異なり、必ず自分が志望する職種の試験内容を把握しましょう。
また、新方式ではプレゼンやグループワークなども実施されるため注意してください。
試験内容については、下記の記事で詳しく解説しています。
>>東京都庁採用試験の倍率と特徴【倍率は低いが難易度は高い】
試験日程
都庁の試験日は職種ごとに異なります。
| 職種 | 試験日 |
| Ⅰ類A | 5月2週目 |
| Ⅰ類B | 4月末 |
| 2類 | 9月1週目 |
| 3類 | 9月1週目 |
| キャリア活用選考 | 8月2週目 |
| 障がい者を対象とした試験 | 9月1週目 |
| 就職氷河期世代を対象とした試験 | 10月中旬 |
最も早い試験であれば、4月末から試験がスタートします。
早い段階で対策を始める必要がありますね。

採用試験に合格するための対策方法

東京都職員の採用試験の難易度を上げているのは、専門試験が実施される点。
専門試験以外に関しては、他の公務員試験と大きく異なりません。
本章では、1次試験と2次試験に分類して解説していきます。
1次試験
1次試験では、下記の3種類が実施されます。
- 教養試験
- 専門試験
- 論文試験
教養試験では、数的処理で得点できるかが鍵になります。
数的処理は、最も出題数が多い上に解法パターンを理解してしまえばほとんどの問題を解けてしまいます。
しかし、解法パターンが身に付くまでに相当な時間がかかるため、早く対策を始めましょう。
専門試験では記述式で、3題出題され2時間で答えなければなりません。
そのため、1題あたり40分600~800字程度しか書けないですね。
基礎的な知識をしっかりと学習しましょう。
論文試験では、1題1時間30分で専門記述試験よりウェイトが重いと言えます。
そのため、教養試験で足切りを避け論文試験では時事対策などを確実に行っておきましょう。

2次試験
2次試験で実施されるのは、口述試験。要は面接試験です。
面接試験のウェイトは年々重たくなっており、人物重視であることは間違いありません。
面接試験の基本は、自己分析です。面接では様々な質問がされますが、自分に関する質問が最も大切です。
行政の数値などを暗記するより、自己分析を最優先して行いましょう。
面接試験に関して、下記の記事で詳しく解説しています。
>>公務員試験の面接対策は3つのステップで進めていこう【全体像とコツを紹介】
予備校をうまく活用する
公務員に最短で合格するためには、プロの力を借りることをおすすめします。
公務員試験はセンター試験などのと異なり、公務員特有の試験対策をしなければなりません。
初学者から独学で挑戦することも可能ですが、非常に難易度が高くおすすめできません。
公務員予備校の講師は、そんな初学者を合格に導くプロです。
予備校の情報については、公務員予備校の基礎知識と選び方のポイント【予備校経験者が徹底解説】を参考にしてください。
2023年から新制度がスタート

東京都人事委員会は以下のような発表を行いました。
大卒者向けの職員採用試験で合格した人が希望すれば、採用が3年間猶予される制度を導入する。
つまり、合格した後に3年間の自由な期間があるということです。
受験生は合格後に海外留学や企業への就職することも可能。
同様の取り組みは国家公務員総合職でも導入されていますが、地方自治体では非常に珍しいですね。
公務員への就職を目指すのもありですが、その前に他の景色も見れるとなると人間としても成長できるでしょう。