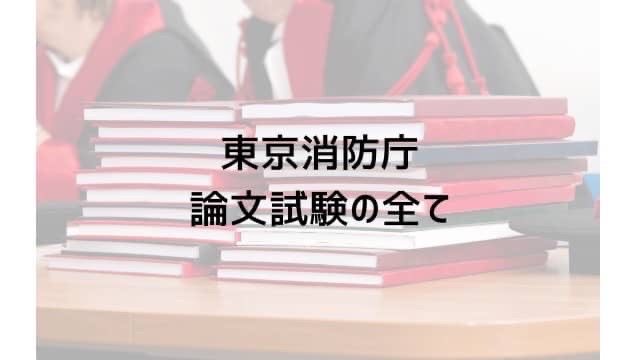
こんにちは、元公務員のヤット(@kantan-koumuin)です。
公務員試験に合格するためのノウハウを解説しています。

東京消防庁の論作文試験は曲者と言われており、毎年受験生の頭を悩ます原因となっています。
東京消防庁の第一次試験において論作文試験は、合否に関わる大変重要な科目。
実は、東京消防庁の論作文試験は特徴があるだけで、対策をしっかりすれば怖くはありません。
なぜなら、僕自身もその特徴を理解し対策した結果、東京消防庁I類の試験を突破した経験があるからです。
その特徴はスバリ2つです。
- 文字数
- 採点方法
この記事では、そんな東京消防庁の論作文に特徴がある背景や具体的な対策法を紹介しています。
この記事を読み終えれば、東京消防庁の論作文試験について知識が深まり、本番の試験までに効率良く対策することができます。
東京消防庁については、採用試験以外にも知っておくべき情報があります。
下記の記事で総合的な情報を掲載しているので、参考にしてください。
>>東京消防庁の総合情報【仕事内容・試験内容・年収】全て解説してみた
目次
東京消防庁の論文試験の概要

東京消防庁の論作文試験はの概要は下記のとおり。
- 課題式
- 類及びII類は論文形式
- Ⅲ類は作文形式
- 文字数は800字〜1200字
- 制限時間は1時間30分
このようになっています。

論文形式の方が難しくなっています。
過去のデータ
東京消防庁では過去に出題された論作文の課題が公開されています。
過去の課題を見ることで東京消防庁が、どんな課題を出題する傾向があるかある程度把握できますよ。

参考にしてみてくださいね。
I類の課題
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現が人間社会にどのような影響を与えるのか、あなたの考えを具体的に述べなさい。
- 下の資料(省略)から傾向を読み取り、行政機関が発信する情報を都民に広く周知するための効果的な方法を考え、具体的に述べなさい。
- 資料「救急車を呼んだ理由」(グラフは省略)から読み取れる課題と対応策について、あなたの考えを具体的に述べなさい。
II類の課題
- 都民から信頼される公務員になるために、あなたが必要だと思うことを2つあげ、その理由を具体的に述べなさい。
- 資料「日本の人口推移」から読み取れる内容について、あなたが感じる問題点を2つあげ、その問題点に対してどのような取組みが必要か、あなたの考えを具体的に述べなさい。
- 消防職員として働く上で信頼関係の重要性をあげ、信頼関係を築くためにあなたはどう取り組んでいくのか述べなさい。
Ⅲ類の課題
- 社会人の義務と責任についてあなたの考えを述べなさい。
- 社会人としての心構えと行動について、あなたの考えを述べなさい。
- あなたが目指す信頼される消防職員像について述べなさい。
お気づきの方も居るかもしれませんが、I類とⅢ類では内容が全く違います。どの類を受験するかによって対策も変わりますね。
それぞれの課題のイメージとしては、
I及びII類→資料を読み解いて自分の考えを述べる
Ⅲ類→自分のことを問われている
こんなイメージで考えると良いです。
論文試験については、下記の記事で詳しく解説しています。ある程度のルールを知っておいた方効率よく対策することができます。
他の消防本部との違い【東京消防庁の特徴】

東京消防庁の論作文試験には、ある特徴があります。
- 文字数
- 採点方法
この2つですね。順番に解説していきます。
文字数
文字数の指定は800字〜1200字。指定文字数の間が400字もあります。
これは少なくても良いというわけではなく、必ず1200字近く書くようにしましょう。
日本語の解釈からすれば、800字以上書いていれば問題ないように感じますが、これが大きな間違い。
仮に801文字しか書いていない場合、どれだけ教養試験で良い点を取っていても第一次試験で不合格になってしまいます。
他の消防本部であれば「600字程度」のような文字制限ですが、東京消防庁の場合は「〜1200字」。
実際に僕が受験した京都市消防局の論作文試験では「600字程度、40分」という課題内容でしたね。

採点方法
東京消防庁では、第一次試験から論作文試験の採点が実施されます。
なぜなら、東京消防庁は日本が誇る消防組織であり受験者数の多さも他の消防本部を圧倒しています。
そのため、教養試験の点数だけで第1次試験の合否を決めてしまうと、第2次試験の対象者が多くなりすぎ採点に支障を来すため。
このような理由から、第1次試験の段階で合否の判定に論作文試験の点数を加算するようにしているのです。
ほとんどの消防本部では、第2次試験以降から採点する方式を採用しています。
試験を突破するための知識【傾向を知っておこう!】
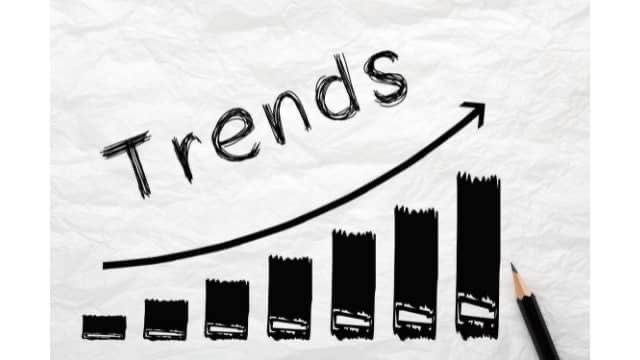
東京消防庁では、試験の傾向があります。
傾向を大まかに掴んでおくことで、ある程度どんな対策が必要か分かるようになりますよ。
課題形式の変化(過去・近年)
東京消防庁で過去に出題されていた課題は「一行問題」(Ⅲ類で出題されるような問題)が多くありました。
しかし、2017年度以降は「グラフ・統計資料を読み取らせて対策を考えさせる課題」に変化しています。
そのため年々、論作文試験の難易度が上がっていると言えます。
今後の出題予測は?
今後も「グラフ・統計資料を読み取らせて対策を考えさせる課題」の出題は継続されるでしょう。
そのため、グラフや統計資料から自分の言葉で考えを書けるような訓練が必要となります。
また、東京消防庁の業務に関係することだけでなく「行政」に関することも課題として出題される可能性があります。
背景としては、公務員として多種多様な業務上の問題に対応するため。
論作文試験突破の鍵とは?【具体的な対策法】

試験を突破するための近道は、公務員試験のプロに添削してもらうこと。
過去の試験では、独学でも論作文試験を突破することは可能でした。
実際のところ、僕自身も受験生時代に独学で第1次試験を突破した過去があります。
しかし、近年はそう簡単ではありません。難易度が上がっていることから独学での受験は非常にリスクがあります。
そこで公務員試験道場では、通信講座の受講をおすすめしています。
学校の選び方(判断基準)
近年、公務員系の学校は数多く存在します。
実際に「どの教育機関を選ぶべきか」の判断基準は難しいものがありますよね。
そこで判断基準の一例として、下記の3つのポイントを参考にしてみてください。
注意するポイント
- 受講料が高額(100万円以上〜)
- レスポンスが遅い
- 専門知識が薄い
このような項目に該当する教育機関には注意するべきでしょう。
おすすめの学校
現在、数多くの学校があるため迷ってしまいますよね。そこでおすすめの学校を紹介します。
公務員試験道場では、東消塾をおすすめしています。
実際に僕自身も受講しましたが、元東京消防庁の講師が実践的な添削などをしてくれます。
詳しくは受講したレビュー記事を参考にしてください。
>>元消防士が東消塾の新プランを徹底レビュー【東京消防庁を目指すなら東消塾!】
まとめ:論文対策はプロの添削が命!

東京消防庁の論文対策は、専門の知識を持ったプロに添削してもらう必要があると言えます。
独学の場合はどうしても主観が先行してしまいます。
そのようなことを防ぐためにも第三者の客観的な眼、しかも専門知識を持ったプロの意見を聞くことが合格への近道です。
記事の要約
- 東京消防庁の特徴は、文字数と採点方法
- 年々、難易度が上がっている
- 試験突破の近道はプロの力を借りること